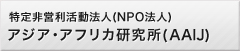現在のページ
- アジア・アフリカ研究所について
目的
この法人は、1961年4月に創立されたアジア・アフリカ研究所の研究・啓蒙活動を受け継ぎ、広くアジア・アフリカ・ラテンアメリカ(AALA)諸国の政治、経済、社会、文化およびAALAをめぐる世界政治と世界経済上の諸問題について、理論的研究、現状分析(情勢分析)の両方面から共同研究・調査・啓蒙を行い、これによって、日本におけるAALA研究水準の向上およびAALA諸国民との友好・協力に貢献することを目的とする。(法人定款 第三条)
Objectives
This corporation, inheriting the activities of research and education from the unincorporated Afro-Asian Institute of Japan which was founded in April 1961, has the following objectives: To conduct joint research, survey and education on both theories and practices of politics, economies, societies and cultures in a wide range of nations in Asia, Africa and Latin America (hereafter referred to as AALA) as well as of AALA-related problems in world politics and world economy; and hereby to contribute to the enhancement of AALA research in Japan and the promotion of friendship and cooperation with AALA peoples. (AAIJ Statute,Article3)
新型コロナ・パンデミック時代を乗り越える Overcoming the COVID-19 Pandemic Era
1961年にアジア・アフリカ研究所が設立され60年を迎えましたが、この60年間において研究所はいろいろな試練を乗り越えて今日に至っています。組織的には、1986年に所則が大改訂され、世代交代しながら幹事会が中心となり活動してきました。さらに、2008年にはNPO法人アジア・アフリカ研究所として新しく理事会(藤田和子初代代表理事)が組織され、2012年からは松下冽代表理事、2016年からは文京洙代表理事と引き継がれて、研究所の活動が継続されました。
この60年間の活動においては、実に多くの研究者がさまざまな形で支援され存続してきました。(研究所ホームページに掲載さている藤田和子論文「資料からたどるアジア・アフリカ研究所の50年」を参照していただければ幸いです。)
また、この60年間は世界にも大きな時代の変化がありました。1991年には戦後続いた「冷戦体制」がソ連社会主義の崩壊で終焉し、新たな時代が開始されました。世界は市場経済に包括される「グローバル資本主義」の時代に突入しました。
研究所の途上国研究はその時代を反映し、それぞれの時期にさまざまな視点からの多くの論文が『アジア・アフリカ研究』に掲載されてきました。
研究所の中心的な事業活動は、学術雑誌『アジア・アフリカ研究』の年4回の定期発行と研究会です。雑誌発行はなんとか継続していますが、2020年からの世界的な新型コロナウイルスの拡大のため、これまで通りの研究会活動は困難となっています。2021年も有効なワクチンや治療薬の普及がない限り、状況の改善は楽観できません。第60巻の特集は「コロナ・パンデミック時代のグローバルサウス」が企画されました。
今日の世界的な「コロナ危機」については2020年4月のIMFの世界経済見通しの報告書において「1930年代の世界恐慌以来で最悪の景気後退」に直面していると表現しています。新型コロナウィルス・パンデミックによって2008年世界金融危機を上回る世界不況に突入し、先進国経済のみならず途上国・新興国経済にも大きな影響がもたらされています。今回のパンデミックは2016年から開始された国連のSDGs(持続可能な開発目標)にもまた大きな衝撃を与えており、再び途上国の人々の貧困化が深刻になりつつあります。世界の人々は新型コロナウィルス・パンデミックをどのように乗り切り、どのようにして先進国と途上国の人々の深刻化する貧困問題を解決するかが重要な課題となっています。それは国連のSDGs実現の中心課題でもあります。これらの問題を研究者のさまざまな視点から考察し、方向性を見出すことは研究所の研究活動にとっても大いに意義あることと考えます。とりわけ、学会の権威主義や伝統主義にこびない若い世代の研究者に期待するものがあります。
また、これからの時代はますますインターネット環境とIT技術の発展が進み、学術雑誌の発行形態も近い将来大きく変化する可能性もあります。しかし、どのようなIT技術と環境が変化しようとも、研究活動を支えるのは研究者自身です。その意味で、60年の長い歴史にもかかわらず、途中で研究者の世代交代があり、次々と若い世代の研究者がアジア・アフリカ研究所の研究活動を引継ぎ、雑誌発行が継続されたこと、また小さな民間の研究機関として生き残ってきたということは、ある意味で奇跡的な感じもしています。それは大きな誇りでもあります。
幸いにも、研究所の理事会の中心メンバーと編集委員会には30代40代の若手中堅の優秀な研究者たちが実務を担っており、心強くもあります。また新しい編集長も長年NGO活動で経験豊富な研究実績もある重田康博理事が就任し、これも心強く感じています。
現在も世界の変化は激しく、次々とこれまでにない新しい社会現象や経済現象が起きています。既存の経済理論や政治理論も常に現実と向かいながら、深く考察されなければなりません。権威主義や伝統主義に依存している既存学問では現代の現実の変化に対応できず説明がつかないことがあります。さまざまな視点から現実世界を分析する必要があります。社会科学にとって権威主義は堕落の道です。これからの研究所の発展は、既存の伝統的理論を疑い、学問の権威主義を排して、研究者の自由で活発な議論と発表が担保されることが重要と思います。特に新しい若い研究者の参加を期待しています。私の役割はそのような若手中堅の研究者を研究所の活動を通じて手助けすることと考えています。
アジア・アフリカ研究所は1961年4月に設立され、21世紀初年の2001年4月創立40周年を迎えました。
20世紀後半は、植民地体制の崩壊と社会主義世界体制の解体を経て、世界の政治・経済秩序が大きく転換した時期でもありました。
アジア・アフリカ研究所はこの激動のなかで、大国主導の植民地体制下に他律的な支配=従属関係の受容を強いられてきたアジア・アフリカ・ラテンアメリカ(AALA)諸国が、その他律性をいかに克服し、新たな発展の道をいかに探求するかに視点をあわせて考究するとともに、アジア唯一の先進資本主義国である日本がはたすべき役割について熟思してきました。
また、グローバリゼーション、すなわち多国籍企業の展開を基軸とする資本主義世界システムの地球大の拡大に関しては、その特質の解明やグローバル化と国民国家および労働・市民運動等の考察に努めてきました。
アジア・アフリカ研究所は、非政府・非営利の学術組織として、この間『アジア・アフリカ研究』誌(月刊および季刊)を発行しつづけ、ベトナムの独立と統一を終始支援して膨大な『資料ベトナム解放史』全3巻を刊行するなど、それぞれの時点で内外のいかなる圧力にも屈することなく、自由な研究の場として機能しえたことを心から誇りとするものであります。
1961年5月、本誌「創刊のことば」は次のように述べています。
「このたび、われわれアジア・アフリカ・ラテンアメリカの研究、調査を専門とする学者、研究者有志が相寄り相集まって、"アジア・アフリカ研究所"を創立した。
本研究所は、このAALA三大陸における民族独立、平和、経済的繁栄、社会的進歩をめざす諸民族の歩みが世界史の画期的な転換をうながす重要なエネルギーの一つであるとする立場から、AALA諸国の政治、経済、社会、文化およびAALAをめぐる世界政治と世界経済上の諸問題について、共同研究の方法を基礎として、(a)理論的・基本的諸問題の研究、(b)現状分析(情勢分析)の両方面から研究調査を行ない、これによって、日本におけるAALA研究水準の向上、およびAALA諸国人民の連帯の強化にいささかなりと貢献しようと考えている。
本月報、すなわち、月刊"アジア・アフリカ研究"は、以上のような本研究所の目的にしたがって刊行される研究調査機関誌である。
われわれ所員一同は、できるだけ早い期間内にわれわれの共同研究の成果が誌上に反映されるような努力をしていくつもりである。
また、同じ情勢分析をするにしても、単なる時事解説でなく、多少とも基本的研究の角度から分析していくことを心がけているつもりである。
読者の方々のご批判をいただきつつ出来るだけいい誌面にしていきたいと念願している。」
今般、アジア・アフリカ研究所は、特定非営利活動促進法に基づく法人として認証され、任意団体から特定非営利活動法入(NPO法人)に移行することとなりました。特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所は、本誌「創刊のことば」の精神に沿って、法人定款で定められたAALAとAALAをめぐる諸問題に関する共同研究・調査・啓蒙活動を実施し、これによって日本におけるAALA研究水準の向上およびAALA諸国民との友好・協力に貢献することをめざします。
上記のようなアジア・アフリカ研究所の目的と歩みをご理解くださる方がた、ことに若い世代の皆さんが共同の研究調査等に積極的に参加されることを期待いたします。
2007年3月
特定非営利活動法人アジア・アフリカ研究所
(あいうえお順、2024年7月7日現在)
理事
| 太田和宏 | (神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授) | |
| 大津健登 | (編集担当、駒沢大学経済学部教授) | |
| 代表理事 | 岡野内正 | (法政大学社会学部教授) |
| 河合恒生 | (岐阜経済大学名誉教授) | |
| 後藤政子 | (神奈川大学名誉教授) | |
| 編集長 | 重田康博 | (宇都宮大学国際学部元教授) |
| 鈴木規夫 | (愛知大学国際コミュニケーション学部教授) | |
| 所 康弘 | (明治大学商学部教授) | |
| 長島怜央 | (東京成徳大学国際学部准教授) | |
| 中野洋一 | (九州国際大学名誉教授) | |
| 福島浩治 | (編集・ホームページ担当、駒澤大学経済学部准教授) | |
| 藤本 博 | (元・南山大学教授) | |
| 松下 冽 | (立命館大学名誉教授) | |
| 文 京洙 | (立命館大学名誉教授) | |
| 山中達也 | (編集担当、駒澤大学経済学部准教授) |
- 監事
- 藤田和子 (宇都宮大学名誉教授)
List of Officials (in alphabetical order, as of June 5, 2021)
- Directors
- FUJIMOTO Hiroshi, Former Professor, Nanzan University
- FUKUSHIMA Koji, Associate Professor, Komazawa University
- GOTO Masako, Professor Emeritus, Kanagawa University
- KAWAI Tsuneo, Professor Emeritus, Gifu Keizai University
- MATSUSHITA Kiyoshi, Professor Emeritus, Ritsumeikan University
- MUN Gyongsu, Professor Emeritus, Ritsumeikan University
- NAGASHIMA Reo, Associate Professor, Tokyo Seitoku University
- NAKANO Yoichi, Professor Emeritus, Kyushu International University
- OKANOUCHI Tadashi, Professor, Hosei University
*Representative Director - OTA Kazuhiro, Professor, Kobe University
- OTSU Kento, Professor, Komazawa University
- SHIGETA Yasuhiro, Former Professor, Utsunomiya University
*Editor-in-Chief - SUZUKI Norio, Professor, Aichi University
- TOKORO Yasuhiro, Professor, Meiji University
- YAMANAKA Tatsuya, Associate Professor, Komazawa University
- Supervisor
- FUJITA A. Kazuko, Professor Emeritus, Utsunomiya University